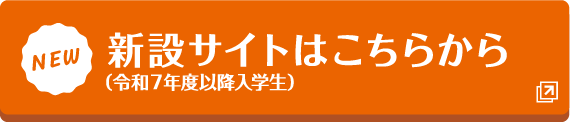環境デザイン学科 学科サイト
自然環境と社会環境の総合的デザインを実践的に学ぶ
自然科学と社会科学の両方を含んだ文理融合教育の下、
自然環境や社会環境の総合的デザインに関わる実践的な知識や技術に基づいて、地域社会が抱える危機をとらえ、
人と自然が共生する持続可能な地域社会を共に築き上げる人材を育成します。
環境サステナビリティコース

本コースでは、自然環境と社会との望ましい関係性を構想できる感性を身に付け、その実現のために必要な調査・計画・管理に関わる知識と技能を修得します。具体的には、自然環境に関わる各種専門分野の知識・技能の横断的・実践的な学修を通じて、様々な観点から自然環境と社会との関係性を考察できる多面的な探求力、多様な関係性の中から重要な課題を発見できる課題発見力、その解決に向けた道筋をデザインできる構想力、そして、その道筋を地域社会の文脈に即して活かすことのできる実践力を身に付けます。
地域デザイン・防災コース
 愛媛県では、南海トラフ地震をはじめとする巨大災害の勃発や環境問題の深刻化が懸念される一方で、グローバリゼーションや少子高齢化に伴う地域コミュニティの衰退が危惧されており、地域社会がいかにして活力ある形で存続できるかが問われています。
愛媛県では、南海トラフ地震をはじめとする巨大災害の勃発や環境問題の深刻化が懸念される一方で、グローバリゼーションや少子高齢化に伴う地域コミュニティの衰退が危惧されており、地域社会がいかにして活力ある形で存続できるかが問われています。
本コースでは、まちづくりや地域防災の現場実務に学生自らが参画し、そこでの活動を通じて実践的な知と技能を養う実践的教育を推進します。それとともに、関連する社会科学諸分野の専門教育を通じて、地域が抱える諸問題の総合的な解決に資するデザイン能力と政策マネジメント能力を身に付けます。
カリキュラム
2024年度以降入学者

- 2023年度入学者のカリキュラム
-

- 2022年度入学者のカリキュラム
-

- 2021年度入学者のカリキュラム
-

- 2020年度入学者のカリキュラム
-

- 2016年度~2019年度入学者のカリキュラム
-

主な研究テーマ
|
|
- 【令和7年度(愛媛大学)入学者選抜以降】学科のアドミッション・ポリシー(AP:入学者受入の方針)
-
(知識・理解)
1.高等学校等で履修する国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語、情報などに関して、高等学校卒業相当の基礎知識と理解力を有している。(思考・判断)
2.目標を達成するために、多面的視点から論理的に考察し、自己の考えをまとめることができる。(興味・関心・意欲・協働)
3.環境サステナビリティや地域デザイン・防災に関心を持ち、次世代の持続可能な地球環境や地域社会の実現に積極的に関わろうとする意欲を有している。
4.社会全体の利益に資する公共心を持って、様々な人々と協働しながら熱意を持って地域社会の課題解決に取り組む姿勢を有している。(技能・表現)
5.他者の意見を理解し、自己の考えをわかりやすく表現できる対話力を有している。<選考方法の趣旨>
【一般選抜 前期日程】
大学入学共通テストでは、高等学校で履修する主要教科・科目について教科書レベルの基礎的な知識を幅広く身につけているかをみるために、5教科5科目を課しています。また、個別学力検査等では、高等学校卒業レベルの基礎知識、及び定性的・定量的分析力をみるために、英語とデータ分析を含んだ総合問題を課すとともに、自然環境や社会環境に関する関心、知識、思考、判断、意欲、協働、表現力等を総合的にみるために面接を課しています。【総合型選抜Ⅰ】
高等学校で履修する範囲の知識や思考、判断力をみるために、総合問題を課しています。また、関心、知識、思考、判断、意欲、協働、表現力等を総合的にみるために、面接とグループディスカッションを課しています。さらに、高校生活における活動歴等を踏まえ、意欲、能力、関心等をみるために、活動報告書、志望理由書等を課しています。
- 学科のカリキュラム・ポリシー(CP:教育課程編成・実施の方針)
-
<教育課程の編成と教育内容>
本学科では、学部カリキュラム・ポリシーに加え、以下の方針に基づいて教育課程を編成します。
・環境デザインを通じた地域社会の持続的な発展の担い手を育成するために、専門教育と課題解決型教育を連動させたカリキュラムを構成します。
・自然環境・社会環境・人間活動の相互関係の理解に関する基礎知識を幅広く学修し、環境サステナビリティ系と地域デザイン・防災系に関わる専門的な知識や技能を順次修得できるように、共通教育、基礎力育成科目群、実践力育成発展科目群や専門力育成科目群を配置します。
・実践力育成発展科目として、環境サステナビリティ系と地域デザイン・防災系に関わるフィールド実習を配置するとともに、これらの結果をまとめ上げ、他者と共有する技能に関わる科目を配置し、環境デザインに必要な総合的な実践力を学修するための科目を配置します。
・環境デザインに必要な自然環境・社会環境・人間活動の相互関係の理解に関する基礎的な知識と技能を学修するとともに、環境サステナビリティ系と地域デザイン・防災系に関する具体的な課題を学び、その理解や解決について体系的に学修するために、学科科目を配置します。
・履修コース科目では、環境サステナビリティ系として、地球環境、持続可能性、生物多様性、環境経済、環境政治、地理科学に関する科目を、地域デザイン・防災系として土木計画、都市計画、景観、防災計画、自然災害に関する科目を配置し、環境デザインに関わる専門的知識と技能を学修します。また、環境デザインに必要な多様な視点や技能を養うために、他学科・他学部科目の履修を推奨します。
<教育方法>
本学科は、初年次より順次、環境デザインに関するコース横断授業科目や専門科目の履修を通じて、環境サステナビリティ系と地域デザイン・防災系に関する知識を身に付けるとともに、並行してPBLやアクティブラーニング手法を用いたフィールド系科目を順次展開し、自然環境や社会環境に関わる調査・問題抽出、課題解決のためのアプローチの手段を学び、環境デザインに関わる知識・技能・態度を実践的に学修します。各コースにおける専門教育方法は以下のとおりです。
・環境サステナビリティコースでは、「環境の状態を調べる分野」「環境を守る分野」「環境を管理する分野」の3つの主要専門分野の講義と国内・海外のフィールドワークやインターンシップを通して、環境と人間の相互作用として環境問題を捉える文理融合の地球環境学の専門知識と技術を学ぶことにより、環境デザイン力を身に付けます。
・地域デザイン・防災コースでは、まちづくりや地域防災の現場実務に学生自らが参画し、そこでの活動を通して実践的な知と技能を養う実践的教育を推進します。また、関連する社会科学諸分野の専門教育を通じて、社会環境と社会との関係を中心とする諸問題の総合的な解決に資するデザイン能力と政策マネジメント能力を身に付けます。
- 学科のディプロマ・ポリシー(DP:卒業認定・学位授与の方針)
-
<教育理念と教育目的>
21世紀に入り、我々の社会は、地球環境問題や巨大災害の勃発をはじめ、その持続性を根底から崩しかねない危機に直面しています。こうした危機の時代にあって、人間と環境の共生のあり方、地域社会のあり方、さらには科学技術のあり方といった根本的な問題が改めて問われています。
本学科では、環境サステナビリティコースと地域デザイン・防災コースの2つのコースを配置し、自然科学と社会科学の両方を含んだ文理融合教育の下、幅広い視点から、人と自然が共生する持続可能な地域社会のあり方を問い直します。そして、自然環境や社会環境の総合的デザインに関わる専門的な知識・技術を養うとともに、環境問題や地域デザイン・防災に関わるフィールドワークを通じて、地域ステークホルダーと協働して地域社会が抱える諸問題の解決に取り組む実践的な素養を身に付けることにより、次世代の持続可能な地球環境や地域社会の実現に貢献することを教育・研究の目的としています。<育成する人材像>
地球規模の環境問題から地域コミュニティの衰退に至るまで、地域社会が抱える諸問題がますます深刻化・複雑化する中、その問題の解決を図る上では、単一の専門分野だけに留まらない幅広い視点から地域社会の問題を捉えるとともに、地域ステークホルダーとの協働により、地域固有の知識や技術を活かしながら地域問題の協働的な解決を導き、持続可能な地域社会を共に築き上げることができる人材が求められています。
本学科では、理系・文系の広範な学問領域における基礎的素養に基づいて、人間と環境との相互関係を理解するとともに、地域ステークホルダーとともに持続可能な地球環境・地域社会の将来ビジョンを創造する実践的なデザイン力とマネジメント力を修得し、持続可能で安寧な地域社会や地球環境の創造に向けて、地域政策や国際政策を運営・推進できる環境デザイン創造人材を育成します。<学習の到達目標>
(知識・実技)
1.理系や文系の広範な学問領域における基礎的素養を有し、これらを合わせて人間と環境との相互関係を理解し、デザインするための専門的・応用的な知識を修得している。(思考・判断)
2.理系及び文系的思考の下、全体を俯瞰する総合的な視座に立ちながら、地域社会・環境の改善に向けた将来ビジョンを策定・調整することができる。(興味・関心・意欲、態度)
3.地域社会・環境のサステナビリティに関する諸課題に対して、自ら積極的に関心をもち続けることができる。
4.地域社会を新たな価値創造へと導こうとする意欲を有し、地域社会・環境のサステナビリティに関する諸課題の解決に取り組むことができる。(技能・表現)
5.適切な調査・分析方法を用いて、自然環境との共生をもたらす地域社会デザインに必要な情報を収集・整理・分析することができる。
6.自らの考えを的確に表現し、他者との間で討論・対話することができる。(リーダーシップ)
7.地域社会・環境の諸課題の解決へ向けて、サーバントリーダーシップを発揮することができる。<卒業認定・学位授与>
社会共創学部の定める教育課程を修め、規定する期間以上在学し、厳格な成績評価に基づき所定の単位を修得し、かつ社会共創 GPA が卒業要件を満たした学生に対して、卒業を認定し学位(学士)を授与します。