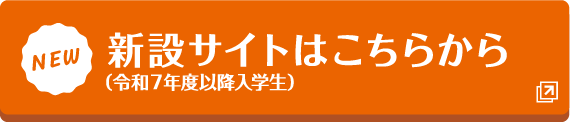授業紹介
フィールド実習
- 学科: 産業マネジメント学科、産業イノベーション学科、環境デザイン学科、地域資源マネジメント学科
- 学年: 2年次
- 教員: 社会共創学部教員
- 科目群:実践力育成科目群
地域社会に向かい合う自分のスタンスを作ろう!
授業内容
この授業では、地域のステークホルダーの方々とのディスカッションやフィールド調査をチームで行うことによって、地域の資源や課題をつかむ力を育成します。ここでは、松山市道後地区での取り組みを紹介しましょう。
こまめに「調査」する

地図を用いながらまちをチェックし、事前調査結果を解釈します
まずは、事前に道後地区の歴史や街の成り立ちなど基礎情報を調べた上で、道後地区のフィールドで調査を行います。現場では、通行人の会話に耳を傾けたり、面白そうな路に入ったり、おいしそうなものを食べたり、お店の人と話したり、五感を使ってまちを観察、調査、記録していきます。大学に帰ってきたら、気づいたこと、感じたことを逃さないうちに、自分で記述したうえで、グループで共有していきます。こうした活動を繰り返しながら、観察した人々の発言や行動に含まれる意味を読み取っていき、徐々に気になる点を絞り込んでいきます。
「問い」をたてる

「問い」に磨きをかけるためのディスカッション
気になる点が出てきたら、それまで集めた情報をもとに「問い」をたてます。そして、フィールドに行ってその問いの答えを調べていきます。たとえば、「外国人観光客はどんなときに外国語表記を必要にしているのか」という問いをたてたら、外国人観光客がどんな行動をとっているのか観察したり、ヒアリングをしたり、外国人向けのゲストハウスの人に話を聞いたりします。そして、自分たちの問いがどの程度、明らかになったのか、はじめの予想通りだったのかなど、再度問い直しをします。つまり、調査のさまざまな時点で調査課題の「問い」を明確にし、それを検証していくなかで、さらに「問い」に磨きをかけていきます。
「思い」を伝える

地域の方々の前でグループの「思い」を発表
試行錯誤の末、グループでつかんだ「問い」の「答え」をパワーポイントとレポートにまとめ、地域の方々の前で報告します。地域の方々から各発表に対してたくさんの的確かつあたたかいコメントを頂き、学生がより深く考える機会になりました。たとえば、以前行った取り組みでは、「道後 駅前の改革」グループは、道後温泉駅前での観光客の滞在時間が10分未満であることを明らかにした上で、その改善策として駅前広場に面した建物のカフェ化など賑わいのある空間を提案しました。「方言」グループは、俳句絵馬、俳句ポストなど、道後にある「ことば」の資源に着目し、店舗での観光客と店員のコミュニケーションを調査した上で、観光客に愛媛に来たことを実感してもらうために、接客などで方言を活用することを提案しました。これらのフィールドワークの「答え」は、グループの「思い」をどれだけ詰められるかが勝負です。
学生から一言
この授業では、1年次に座学で学んだことをもとに、実際にフィールドに出てより知識の理解を深めるとともに、実践的な調査を行ってきました。調査では、実際にステークホルダーの方とのお話し、市役所への聞き取り調査、文献調査などを行いました。毎週の授業後には、その日行った調査の報告をし、先生にアドバイスをいただきながら、より深く地域と関わることができました。最終のプレゼン発表では、これまで調査したことをまとめ、活性化のための提案をステークホルダーの方の前で行いました。普段何気なく歩くところでも、目的をもって歩くことで、新たな発見や、地域の抱える課題が見えてきました。大学生という立場から地域社会を見つめ直し、よりよい社会を共に創るための第一歩となったと実感しています。
教員から一言
「地域に向かい合う自分のスタンスをつくる」とはどういうことでしょう。地域に何度も足を運んでいるうちに、自分が気になるツボ(興味や関心)が段々とわかってきます。そうすると、地域の人に話をどんどん聞きたくなる、じーと観察したくなる、昔の資料を丁寧に調べたくなる、関連する専門分野を深く知りたくなるなど、色々な方法で地域と自分との距離を縮めていくことになります。こうした活動を重ねていくことにより、地域の方々の見方も頭に入れながら、集めた事実を自分なりの見方、観点で考えることができるようになります。この観点(どこから何をみるか)が自分のスタンスになります。どのようなスタンスであっても、「自分の言葉で語る」行為はとても重要です。自分の考えを他の人に伝えるのは責任が伴うからです。フィールド実習がこうした感覚をみがく第一歩になればうれしく思います。