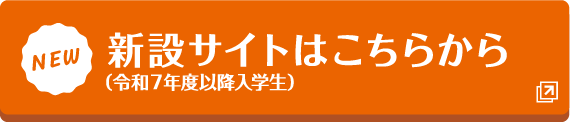お知らせ詳細
2017.08.01 行事
社会共創コンテスト2017受賞作品へのコメント
グランプリ
地域課題部門
伝統的なお酢産業再興作戦 ~日本独自の発酵産業の文化的・科学的価値~
小山 絵凪[愛媛大学附属高等学校]
本研究はお酢を「文化的価値」と「科学的価値」の両面において掘り下げており、着眼点および研究成果が高く評価できる。論理的な構成で、問題点の把握や解決策の提案が明確に記述されている。地域の現状を踏まえた提案にマーケティングの要素を加えるなど、酢屋の復活、振興を予感させる内容である。お酢に関する情報を地域から発信していくアイデアが効果的であり、他領域への波及効果も期待できる。酢酸菌セルロースの新素材の具体的特徴や当該プロジェクトの遂行に係る課題を継続的に研究していただきたい。
研究・探究部門
讃岐うどんが海を汚さないために
秋山 舜 中村 健吾 山口 侑華[香川県立観音寺第一高等学校]
讃岐うどんブームの裏の部分である「ゆで汁の廃液問題」に着目した地域性の高い研究である。仮説を基に,実験を丁寧に重ねることで最適な結論を導き出した。さらに,得られた結果を実用化レベルにまで応用する手法を具体的に示すなど,非常に完成度の高い研究となっている。
準グランプリ
地域課題部門
エコdeヘルシータウン恵那・山岡を元気に! ~寒天で町おこしを・・・~
山口 瑞貴 遠山 佳希 中島 優樹[岐阜県立恵那農業高等学校]
本研究は地域の課題を正確に捉え、地域資源を有効に活用した課題設定がユニークであり、研究テーマの設定も適切である。地域のステークホルダーと協働しながら、寒天カスおよび細寒天の商品開発を実践しており、本格的な商品化が進み、寒天での町おこしが社会への実装が見込まれる。実験・分析結果が分かりやすく、本取組みの持続可能性が高く評価できる。本研究成果の商品化への実現に向けて引き続き頑張っていただきたい。
研究・探究部門
日本の幼児教育内容を カンボジア保育士に動画で伝える事は有益か?
岡崎 修久 工藤 諒万 安廣 佳織 時光 孝汰[岡山学芸館高等学校]
日本人にとってごく普通の幼児教育が、他国では貴重な「教育資源」となり得ることを証明した非常に独創性の高い研究である。各分野の専門家への聞き取り調査を通して、動画のコンテンツ作成や編集作業も丁寧に行われていた。カンボジア人保育士へのアンケート結果も綿密に分析がなされており、波及効果は高い。
特別賞
記憶から記録へ、そして記録から記憶へと ~過去の巨大地震を伝える~
武智 優 [愛媛県立伊予高等学校]
フィールドワークにおける調べる、考える、発表するというサイクルが他の研究と比べて極めて優れている。課題を挙げるとすると、聞き取り調査のサンプル数が少ない点である。今後、地域のステークホルダーとこの課題についてどのように関わっていくかが鍵となるだろう。武智さんの頑張りを私たち学生審査員は評価した。(学生審査員)
ミルクイ貝の成長に及ぼす養殖基質の影響
福村 征竜 [山口県立周防大島高等学校]
他の研究よりも先行研究を客観的に評価し、その結果を用いて独自の研究に仕上げている点で評価できる。具体的な実験結果のグラフや写真などを多用しているため、他の研究に比べてが客観性が増した。目的をさらに具体化させ、地域のステークホルダーと関わっていくことでこの研究が身を結ぶことを願う。 (学生審査員)
奨励賞
地域課題部門
「商工連携」と「家庭科」で挑戦する ものづくり・まちづくり ~伝統工芸品「柳井縞」の地域ブランド化に向けて~
関永 佳奈実 中岡 祥乃 森田 愛菜 坂野 日菜 新田 実桜 倉増 紗希[山口県立柳井商工高等学校]
伊東 澪南 俵 絵里奈 岡本 美歩 城市 遥香[山口県立厚狭高等学校]
先行取組みの課題を踏まえたうえ、他学校、ステークホルダーとの協働、統合が図られている点が高く評価できる。ドレス製作をどうPRし活性化していくのかについての取組み、考察が行われ、研究の持続可能性が認められる。
世羅茶復活プロジェクト 地域の新たな資源 ~世羅茶花を世界に広げよう~
嶽 太智 木城 勇人 是竹 海音 谷川 雅哉 西尾 伊織 福原 奈緒 藤谷 将太 矢口 晃太[広島県立世羅高等学校]
世羅茶というローカルフードの再生からそのグローバルな展開を見据えたスケールの大きいアイデアである。特に、茶花に関しては、低管理下にある茶畑ではないと見出せないことから、怪我の功名的なストーリー性のある地域資源であり、これに価値を見出した着眼点を評価したい。茶花に関する取り組みは、今年度から始まった取り組みということもあり、まだ具体性は低いものの、それだけに今後の展開に期待が持てる。ぜひ後輩たちに自らの経験を伝え、再チャレンジをしてほしい。
商店街を町の顔に!
森実 夏海 [愛媛県立川之江高等学校]
商店街の再生というありていなテーマではあるが、調査の過程に応募者の気づきが複数含まれており、それを丁寧に踏まえた論理構成になっている点に好感が持てる。また、最終的な提案も調査結果を踏まえて一生懸命に考えたことが伝わる提案である。加えて、多くの作品がパソコンでの制作によるものであったのに対し、本作品は手書きによる制作であったことに、ビジュアル上の工夫と温かみを感じさせるものであった。今後は中小企業庁「頑張る商店街77選」などの活性化に取り組む全国の商店街の事例から学び、様々な商店街活性化の方策について学びを深めていただきたい。
伝統産業の後継者不足を解決する移住希望者とのマッチングサイトの可能性 ~「リクナビtrad」は日本の伝統産業の救世主になるか~
藤原 麻希 [岡山学芸館高等学校]
地域の伝統産業の後継者問題はより深刻になっていく。その解決方法に移住希望者とのマッチングと、「リクナビtrad」という具体的な方法を提案したのは独自的で興味深い。伝統産業の継続も移住者の増加も、地域社会に必要なことであるが、両者をいかにつなぐかがテーマである。応募者は、両者のニーズを自らの調査で丹念に調べ、マッチングの仕掛けを新たに開発しようとしている。この「リクナビtrad」の進化に期待したい。
いなか者の野望 〜エコストーブを使った小型発電の取り組み〜
江森 圭介 難波 翔大 村上 倖大 松田 宗一郎 [岡山県立真庭高等学校]
地元間伐材の有効活用という視点から、火力発電とペルチェ素子を利用したエネルギーの利活用という着眼点が大変良い。研究が社会科学、自然科学の両面から行われた点は高く評価できる。社会的な実装へどうつなげていくのか、今後の取組みに期待したい。
中山間地域の高齢者が安心して暮らせるサービスについて
白幡 直也 上西 倫太朗 [広島県立庄原実業高等学校]
まず、300を超える膨大な数の聞取り対象に圧倒される。また、提案である相互扶助システムのアイデアは非常に興味深く、財源を含めた詳細まで詰められており、よく検討した跡が見て取れる提案である。特に、自らの高校の立ち位置をよく検討した上で、高校OBのネットワーク化による相互扶助システムは、高校や行政などのサポートが得られれば、十分現実味のあるアイデアであろう。今後も実践を重ねて、再チャレンジを期待したい。
「愛媛の伝統工芸品を全国に発信!!2017えひめ国体ガチャガチャ大作戦」—愛媛の心を伝えたい 愛媛の心を応援したい—
北尾 綾乃 [愛媛県立北条高等学校]
重厚なイメージのある工芸品と軽妙なイメージのカプセルトイとを組み合わせた意外性のあるアイデアであり、かつ、実現可能性の高そうなアイデアであることが評価される。ただし、カプセルトイの生産に言及されていなかったのが残念。職人監修のもと福祉作業所などにカプセルトイを製作してもらうなどの社会的に広がりのあるアイデアが欲しい。このあたりがクリアになれば、十分実現可能性の高く、かつ、話題性のあるアイデアとなるのではないだろうか。ぜひ、再チャレンジに期待したい。
廃校のプールを利用した毒なしフグの養殖
江上 陽大 [愛知真和学園大成高等学校]
フグ調理師免許がフグの市場拡大の妨げになっていることを、説得力を伴って示すことができており、その解決策として「毒なしフグ」を提示した野心的な提案である。また、毒なしフグの生産が廃校活用だけではなく雇用創出や観光資源の創出など、様々な課題を解決しうる提案として考察されており、その総合性を評価できる。今後も総合的な視野から、様々な課題解決に取り組んで頂きたい。
Twitterを活用した地域コミュニティの継承 〜伝統行事をまもる意義とは〜
武村 拓弥 [愛媛県立三島高等学校]
人と人をつなぐツールとしてツイッターを提案することに、目新しさはもう無い。しかし本作品の意味はそこにあるのでない。応募者の問題意識の高さ、そして行動力であり、大きく評価したい。伝統的行事は地域社会の一部分として、その必要性において行われてきたが、昨今の地域内部の価値観の変化が衰退の原因と探る。そしてツイッターの持つ、人を引き寄せ新たな価値観を生み出す力学を大いに利用し解決につなげようと意欲的である。
USHIONI ~牛鬼で宇和島の未来を救え~
芳谷 華林 宇都宮 梨那 鶴井 遼 中島 稜巌 [愛媛県立宇和島南中等教育学校]
地域にもともとある「祭り」を地域活性化に再活用する試み。本作品の特徴は、類似する祭りと比較研究し、具体的な活性化方法を導き出そうとするプロセスである。宇和島の牛鬼祭りが世界的に見て、どんな祭りなのかを冷静に分析することで、その特筆すべき点が見えてくる。そこに文化的な意義と新しい価値を見出そうとするのである。大いに評価したい。牛鬼祭りが地域社会の新たな「身近な存在」として定着することを期待したい。
みんなで詠媛 〜愛媛を詠もうプロジェクト〜
森野 莉穂 [愛媛大学附属高等学校]
俳句や方言は、言葉を介したコミュニケーションの本質を表象してくれる。現在の状況は、地域社会の経済的衰退だけでなく、コミュニケーションの衰退と警鐘する。実は極めて重要な指摘である。一方で超少子高齢化のなかでも地域社会が生き生きとあり続けるために、俳句や方言がどうあれば良いのか、どんな行動が必要なのか、可能性を探る。これもまた重要な視点である。これまでにないアプローチであり、研究の先を早く見てみたい。
人の集まりをデザインする
藤岡 祐太 [愛媛県立松山西中等教育学校]
高校生が自分たちだけの手で地域コミュニティを活性化させるモデルを提示した点が意義深い。施設をつくること、運用することを自治という概念を用い示し、地域社会のひとつのあり方の試みが評価できる。このモデルを地域社会と共にどう発展させていくのか、生徒以外に関わる問題としての展開を、今後の取組みとして期待したい。
Welcome to Matsuno
山田 真梨子 [愛媛県立北宇和高等学校]
地元松野町の地域資源である美しい自然を生かして、「滑床英語キャンプで町おこし」の提案が面白い。自身が海外留学の際に、観光パンフレット(英語版)を用いて松野町を紹介した体験から生まれたアイデアであろう。ローカル×グロバールの必要性及び重要性はよく伝わる。このアイデアの具現化に向けて、発信を続けていただきたい。
研究・探究部門
風早 HOP!STEP!!JUMP!!! HOJO NEW CRAFT 風早焼
越智 鈴菜 村上 穂香 [愛媛県立北条高等学校]
地場産業である菊間瓦と砥部焼の特徴を生かして新たな工芸品を創出する地域おこしに関する取り組みである。研究過程で予想に反する結果がでたが、新たな視点により解決策へ導いていた。新たな工芸品として地域活性化に貢献できると考えられる。
食品着色料の色変化と応用
新﨑 怜 [愛媛大学附属高等学校]
染料がある特定条件で色変化する要因について、詳細な検証実験が行われた。得られた結果から導かれた結論も妥当なもので、かなり本格的な研究であった。具体的な用途開発に期待が持てる内容である。
アコヤガイ貝殻粉末による水質浄化 ―産業廃棄物の有効活用―
梅村 ひとみ 大加田 華実 中村 理紗 栗木 裕梨 [宇和島東高等学校]
廃棄物であるアコヤ貝殻を重金属除去に活用する研究であり、かなり詳細に実験がなされていた。これらの成果が排水処理に活用できれば、環境問題のみならず廃棄物問題の解決につながると考えられ、波及効果は大きいと考えられる。