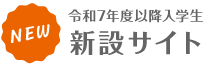授業紹介
観光文化論
- 学科: 地域資源マネジメント学科
- 学年: 2年次
- 教員: 井口 梓
- 科目群:専門力育成科目群
授業のねらい
近年、レスポンシブル・ツーリズム(責任のある観光)やサステイナブル・ツーリズム(持続可能な観光)に象徴されるように、地域社会において観光の在り方が問われています。その一つとして、持続的なまちづくり活動の推進を前提に、そのまちづくりの魅力を観光資源とする「まちづくり型観光」の理念を理解することが必要となっています。本講義では、様々な地域における観光事象や観光地形成の事例を通して文化継承に資する観光の在り方や、地域社会の発展に呼応したサステイナブル・ツーリズムの実践について学びます。
授業内容

観光マップを使って課題検討
文化を活かした観光まちづくりとは、地域が主体となって自然、文化、歴史、産業、人材など、地域のあらゆる資源を活かすことによって地域内外の交流を促進し、活力あるまちを実現していく活動です。つまり、地域の固有性、多様性が観光客にとって異なる地域で触れる「非日常性」(観光対象としての魅力)であり、観光地におけるまちづくりと観光の持続的な発展を考えていくことが重要です。
「観光」は大学で初めて学ぶ専門科目です。本講義では最初に、観光の基礎的な理論や概念(観光まちづくりの概念、観光の定義、観光資源の分類)を学びます。これらを学んだうえで、観光まちづくりの様々な実践事例を4つのトピックから学びます。1つ目のトピックは、文化と観光の関係性へのアプローチです。事例は、文化遺産を継承するために、文化資源管理と観光振興を1つのまちづくりのシステムとして運営している沖縄県竹富島です。2つ目のトピックは、エコミュージアム・フィールドミュージアムと観光まちづくりの仕組みについて、全国の取り組み事例をもとに学びます。3つ目のトピックは、スポーツと地域の立地特性(農村観光)を活かした観光実践として、テニスを観光振興に取り入れた千葉県白子町の事例から、スポーツ観光の課題と可能性を学びます。4つ目のトピックは、エコツーリズムです。地域の自然環境や歴史文化等、地域社会に負荷の無い、よりよいまちづくりに資する観光のあり方を国内外の実践を通して学びます。
本授業の特徴は、理論と実践が往還できるように、4つのトピックの間に、ゲストスピーカーによる課題授業を取り入れている点です。2023年の講義では、新居浜市・マイントピア別子の職員の方々が、さらに四国中央市の職員、地域おこし協力隊の方々がゲストして登壇し、それぞれの地域の現状と課題について投げかけ、受講生は学んだ観光学の知識を活かして課題について検討しました。観光マップや観光パンフレットを使いながら、観光情報の発信方法や、観光コンテンツの企画、着地型観光のアイディアなどを検討します。こうした観光学の専門知識を活かした実践への提言は、講義後に、自治体の観光振興策やまちづくり計画、観光イベント等に採用されています。
教員から一言
「観光」というと、実践的なイメージがありますが、人文社会科学をはじめ、様々な専門から学術的にアプローチすることができる学問分野の一つでもあります。観光に関する情報発信、観光地経営、観光行動(動機)、観光心理・意思決定、観光経験、観光とICT、観光と文化、観光と地域社会等、観光をめぐる研究は幅広くあり、これこそが大学で観光を学ぶ醍醐味でもあります。観光や観光まちづくりの実践活動に関心のある学生さんのみならず、「観光を科学する」ことに関心のある学生さん、ぜひ「観光」を学んでみてください。
- 沖縄県竹富島の文化的な景観
- プロスポーツ誘致によるスポーツ観光
- ゲスト講義の様子(新居浜市)