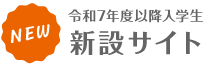学部長裁量経費等プロジェクト
社会共創学部「学部長裁量経費等」によるプロジェクト成果報告書
社会共創学部は、「地域社会に持続可能な発展をもたらす」という設置理念を掲げ、地域の多様なステークホルダーとの協働を基軸とするトランスディシプリナリー手法(社会課題に対して、研究者と社会のステークホルダーが一緒に解決に向けて話し合い、取り組む手法)を導入しています。これは、設置理念を実現するために不可欠となる、学部教育・研究の基本であるという認識のもと、社会共創学部ではこの手法を用いることを積極的に推進しています。
設置理念を実現するため、トランスディシプリナリー手法の多義性・多様性を理解した上で、トランスディシプリナリー教育・研究・地域づくりを積極的に推進できる教員の育成を目的とし、重点的資金配分を2種目(学部長裁量経費・伊予銀行寄附講座)にて行っています。
採択されたプロジェクトチームによる成果報告書は以下のとおりです。ぜひご覧ください。
令和6年度
<学部長裁量経費>
太陽光パネル循環利用スキーム構築にむけて ―太陽光パネル循環利用に関する認識の分析からー
代表者:李 賢映(環境デザイン学科)
愛南町における藻場調査活動のための環境DNA分析技術の開発
代表者:竹内 久登(産業イノベーション学科)
障がい者支援のためのサイボーグ技術活用:愛媛県における自立生活センターとの実践型共同研究
代表者:折戸 洋子(産業マネジメント学科)
地域の力を引き出す「当事地研究」の共同実践:野村町「YUI-GONプロジェクト」を事例として
代表者:羽鳥 剛史(環境デザイン学科)
<伊予銀行寄附講座>
養殖海域に生息する赤潮殺藻細菌の特性解析:環境低負荷型赤潮防除法の開発を目指して
代表者:清水 園子(産業イノベーション学科)
大学間交流協定に基づく海外フィールド実習のあり方と教育研究活動の海外展開 ~カンボジア国立バッタンバン大学との交流を目指して~
代表者:バンダリ・ネトラ・プラカシュ(環境デザイン学科)
愛大「マルチスピーシーズ・キャンパス」の実現に向けた研究活動
代表者:ルプレヒト・クリストフ(環境デザイン学科)
社会共創学部「学部長裁量経費等」による準正課プロジェクト成果報告書
令和6年度
離島の環境問題プロジェクト~空き家へのアプローチから~
代表者:竹島 久美子(地域資源マネジメント学科)
久万高原町柳谷地区におけるアウトドア観光による地域づくり
代表者:山藤 篤(地域資源マネジメント学科)
DX時代における飲食店のクチコミの活用
代表者:折戸 洋子(産業マネジメント学科)
愛媛県西予市の養蚕文化の未来可能性の探索と実践の学び
代表者:榊原 正幸(環境デザイン学科)
「真珠玉リキュール酒」の開発プロジェクト
代表者:寺谷 亮司(地域資源マネジメント学科)
東温市中小企業調査および魅力発信パンフレット作成
代表者:岡本 隆(産業マネジメント学科)