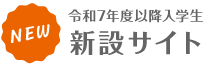報告書
日本では、2012年から始まった固定価格買取制度(Feed-in Tariff:FIT)を機に再生可能エネルギーの普及が進んでいます。太陽光発電の設置も2012年を機に急速に進んだため、太陽光パネルの取り外しは2030年代半ば~2040年代半ばにかけて集中されることが懸念されています。
愛媛県では、2000年度と全国的にも早い時期から太陽光発電設置補助を開始したため、太陽光パネルの取り外しも他県に比べ早い時期に始まると予想されています。太陽光発電を長く使い、取り外す時期を伸ばすことは、資源の有効活用はもちろん、最終処分場の逼迫の軽減にも大きく貢献できます。
FIT法が施行された2012年当時は「保守点検の実施」が義務とされる太陽光発電は、FIT認定を受けた出力50kW以上の太陽光発電のみでした。ところが、保守点検や維持管理をしない状態が続き、様々な問題が浮上することを受け、2017年4月のFIT法の改正(再生可能エネルギー特別措置法の一部を改正する法律の制定)の際に、メンテナンス義務化の対象設備が変更され、50kW未満の住宅用太陽光発電まで対象が拡大されました(なお、FIT認定を受けていない太陽光発電でも出力50kW以上の場合は、電気事業法によって保守点検が義務となっています)。
現実には、保守点検が義務化されてはいるものの、2019年時点においても7割が保守点検を実施していませんでした(Consumer Safety Investigation Commission 2019)。太陽光発電システムは保守点検を行うことで、発電効率の低下や故障などのリスク低減はもちろん、長く使うことを可能にし最終処分場の飽和をやわらげるため、太陽光発電の保守点検の実施は循環経済の達成にとても重要です。
本調査では、愛媛県内太陽光発電設置者(家庭553世帯・企業128世帯)を対象に、太陽光発電保守点検に関する認識・実施可否、太陽光発電パネルのリサイクル・リユースに関する意識調査を行いました。詳細は近日論文で発表を予定しており、本報告書では調査結果のうち数点のみ抽出し、掲載します。
まず、太陽光発電設備の保守点検の義務化に関しては、企業は5割程度、家庭は2割程度しか認識していませんでした(図1)。保守点検の頻度においても、定期的に保守点検を行っている企業は5割、家庭は2.5割程度と、保守点検が普及していないことが明らかになりました(図2)。太陽光発電パネルのリサイクルやリユースに関する認知度も、保守点検義務化の認知度と同様の低さでした(図3、図4)。保守点検義務化の認知経路は、企業、家庭のどちらも「太陽光パネル設置業者」が最も多く、その次が「テレビ・新聞」であったため、これらの経路を通したより積極的な啓発活動が必要だと考えます(図5)。
代表者:李 賢映(環境デザイン学科)