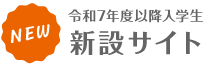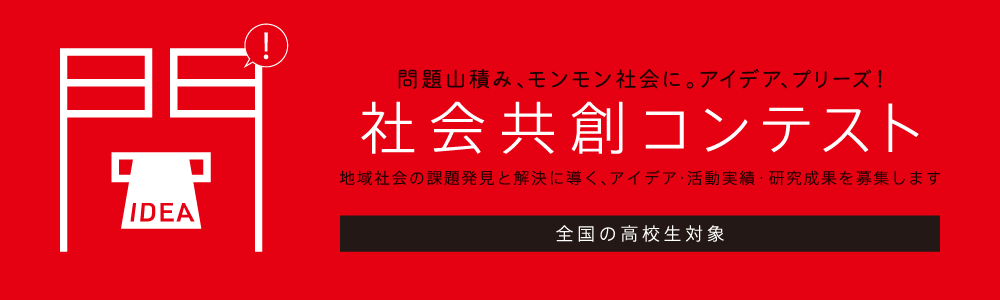
社会共創コンテスト2023
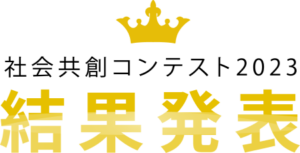 「社会共創コンテスト2023」にたくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。
「社会共創コンテスト2023」にたくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。地域の発展を願う高校生からユニークなアイデアが集まりました。
その素晴らしい応募作品の中から、見事入賞された20作品を発表いたします。
GRAND PRIZEグランプリ
地域課題部門
- マコモの飼料化プロジェクト~持続可能な地域社会の実現に向けて~
松園 倭知 串田 宰
小野田 将太 園田 智也 池上 大耀 馬谷 美好 村上 心愛 平野 結菜 森下 葉月 梅田 武史[おかやま山陽高等学校]
研究・探究・DS部門
- 大門高校周辺のチョウ類の分布と食餌植物の研究~バタフライガーデンづくりに向けて~
-
矢冨 綾乃 長原 梨彩 赤木 公晃 赤木 貫晃 矢冨 紗季[広島県立大門高等学校]
SECOND PRIZE準グランプリ
地域課題部門
-
環境に配慮した果実袋の開発~「バショウ」から始まるサスティナブルな農業~
宇都宮 美虹 大久保 勇那 川口 莉乃 力石 侑士 松平 蓮 仲田 隼人 松浦 花奈 武田 鈴[大洲農業高等学校]
研究・探究・DS部門
- 地図×データで命を守る~宮崎県内の地震・大雨被害のGISによる分析~
-
児玉 祐直 黒木 海音 坂元 最 中竹 美優莉[宮崎県立五ヶ瀬中等高等学校]
SPECIAL PRIZE特別賞
-
地域課題部門
-
都市部の駅で異物混入を防ぐリサイクルボックス
中村 凜 木原 悠太 守安 巧 鈴木 優之介 [本郷高等学校] -
研究・探究・DS部門
-
農業排水による四万十川濁水の低減を目指した貝殻の活用地域の環境問題の解決に向けた理数科生の取組
薬師寺 晃久 小松 凌大 中井 千聖 村田 萌桃 薬師神 杏美 水野 陽向[愛媛県立宇和島東高等学校]
ENCOURAGING PRIZE奨励賞
地域課題部門
- BANKAN×STUDENT オペレーション環 MISSION1:未来につながる栽培を始める
- 山田 愛加 荒木 雄斗 幸田 七海 中谷 渚 安田 亜侑香[愛媛県立南宇和高等学校]
- 共存型稲作の検討と有機農業普及への活動~田んぼの嫌われ者、ジャンボタニシで無農薬に挑戦~
- 岡田 愛生 臼坂 奏音 越智 愛季 笘下 あやの 小柳 治憲 児島 我空 市村 朔 野村 知波[愛媛大学附属高等学校]
- 松山市の海岸におけるマイクロプラスチック汚染の実態調査と対策に向けた啓発活動
- 村上 陽向 近藤 百々花 門田 未来 廣江 実采 蔵野 美結[愛媛大学附属高等学校]
- ムクナ豆プロジェクト ~No(農・脳・否)”の活性化を目指して~
- 川上 咲樹 高橋 亜珠 髙橋 未来 小野 未優菜 永瀬 蓮華 田中 優梨[愛媛県立西条農業高等学校]
- 金沢でオーバーツーリズムを起こさないために
- 佐藤 里彩 白江 愛華 勝見 碧[金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校]
- スマートに農業活性化!普及に向けた農業コンサルタントビジネス
- 武方 愛夢 丹 陸翔 立脇 翔[愛媛県立西条農業高等学校]
- 自発的に取り組むフードドライブ~地域と連携した食料支援~
- 相原 光希[愛媛大学附属高等学校]
- インクルーシブな社会を構築するために
- 高橋 暖和[神奈川県立平塚中等教育学校]
- 小学生とシニアをつなぐ 地域防災イベント 炊き出し練習
- 小島 圭一郎 工藤 義之 木村 凌太 清水 陽介 田邉 涼 二木 倭[岡山県立玉野光南高等学校]
- 市⺠通報システムを利⽤した歩道の段差の改善 -⾼鍋町に潜む段差の原因の調査と改善案の提案-
- 尾﨑 光 諸冨 優海[宮崎県立高鍋高等学校]
- 高齢者と若者に交流の場を
- 岡本 直華 内田 奈那[福井県立若狭高等学校]
研究・探究・DS部門
- アコヤ貝を用いた制酸薬の合成
- 藤江 栞里 大野 衣槻 清水 和奏 細川 惺菜[愛媛県立宇和島東高等学校]
- Finland×Japan 読解力って・・・何!?
- 木村 香乃音 須貝 咲那 小熊 優衣[栃木県立佐野高等学校]
審査委員長総評

愛媛大学社会共創学部長 徐 祝旗
社会共創コンテスト2023には、全国各地から690作品の応募がありました。高校生の皆さん並びにご指導いただいた各高校の先生方、地域の皆さまに深く感謝申し上げます。両部門の応募作品総数は昨年の299から約400作品増加し、審査には大変多くの時間を費やしました。また、順位付けも大変苦慮しましたが、入賞された皆さんの作品は本当に質の高いものばかりでした。(ご入賞おめでとうございます。)
今年度の入賞作品を概括しますと、主に以下の3点の特徴があります。
一つ目は知的活動に富んでいる点です。
自らの学びの場の生物多様性に向けたバタフライガーデンづくりの活動では蝶と食餌植物の分布や関係性の調査、生産者の高齢化に対応した晩柑の低樹高栽培の実験では剪定と密植調査、アコヤ貝を用いた制酸薬の合成では大学教員の指導の下での科学実験などが示してくれたように、多様な課題に対して高校生ならではの知的好奇心に満ちたテーマを適切に設定し、知識を活用した科学的なアプローチを用いる作品が多く見受けられました。
二つ目は地道な協働、積極的な発信が実る点です。
複雑化や多様化が顕著である地域課題に対して、大学、行政、企業、住民、ステークホルダーの皆さまと協働し、ご支援をいただきながら活動成果につながる地道な努力が感じられる作品が多く見受けられました。大学や地元の環境団体・中学生等との連携による松山市の海岸におけるマイクロプラスチック汚染の実態調査、企業・交通機関・役所へのヒアリング調査の結果を基にした都市部の駅における異物混入を防ぐためのリサイクルボックスの設置など、高校の総合探究のコンテンツを遥かに超えた充実な協働でした。
三つ目は社会実装レベルにほぼ到達している点です。
マコモの飼料化プロジェクトでは、地域の特産物である「里庄まこもたけ」を使用して地産地消と家畜飼料の国産化に向けたマコモの調査のみならず、飼料化の実用化に向けた取組、さらには収支計算表の作成まで行っています。環境に配慮した果実袋の開発では、廃プラスチックやブドウの着色不良等の地域課題を解決するために、芭蕉和紙を用いた果実袋の制作に留まらず、開発した果実袋を使用して試験栽培を実施し、着色に改善がみられるなどサスティナブルな農業への期待が高まる作品でした。また、南海トラフ地震の発生に備え、地理情報を活用した具体的な防災対策を策定するなど、アイデアを頭に留めることなく、社会実装に向けた試みを着実に進展させ、実を結んだ点が高く評価できます。
少子化が進む中、各地で高校の再編も始まっています。総合的な探究の学習成果を活かし、地域社会に関する学びや、特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学習が今後はますます増えると思います。また、高校と大学が協力し合う必要性が高まっています。社会共創コンテストは、高校生の課外活動や課題研究を評価し、社会へ発信する機能がすでに定着しています。失敗を恐れず新しい試練に立ち向かう高校生のチャレンジは、これからも続くでしょう。「社会共創コンテスト2024」で若き熱い想いと再会したいです。
社会共創コンテスト2023表彰式
令和5年7月15日(土)、愛媛大学南加記念ホールにて「社会共創コンテスト2023」表彰式を開催しました。
日時:令和5年7月15日(土) 13時~14時30分
場所:愛媛大学南加記念ホール
「社会共創コンテスト2023表彰式」の動画は、こちら。 ※ 制作・著作 愛媛CATV
- 社会共創コンテスト2019表彰式の記事
- 社会共創コンテスト2018表彰式の記事
- 社会共創コンテスト2017表彰式の記事
(社会共創コンテスト2020及び2021は、表彰式の開催を中止しております。)